家族葬は、家族や近親者のみで行われる葬儀のスタイルで、少しずつ浸透してきました。しかし、家族葬と一般葬の違いや告別式の流れなど、家族葬について詳しく知らない方も少なくありません。
なかには「家族葬は告別式のみ」や、反対に「家族葬は告別式なし」と考えている方もいらっしゃいます。家族葬や告別式についてしっかり把握しておかなければ、参列者に慌ただしい様子を見せることになりかねません。
そこで本記事では、下記についてまとめました。
- 告別式と葬儀の違い
- 家族葬における告別式の流れ
- 告別式にかかる時間
この記事を読むと家族葬における告別式について分かるため、これから初めての家族葬を執り行う方におすすめです。
告別式とは?葬儀との違い
告別式とは、故人に別れを告げる式典のことです。遺族はもちろん、仕事の関係者や近隣住民など、一般の参列者も参加できます。
一方で、葬儀は遺族や親しい友人などが参加する儀式です。葬儀と告別式は続けて行われるのが一般的で、その間に明確な区切りはありません。
そのため、最近は葬儀と告別式の言葉の定義も曖昧になり、「葬儀」のなかに告別式も含まれるケースもあります。
なお、家族葬と告別式が混同されるケースもありますが、家族葬は葬式自体のスタイルです。家族葬のなかには通夜・葬儀・告別式・火葬など、基本的にはすべての儀式が含まれています。
家族葬における告別式の考え方
家族葬とは、遺族や近親者のみで執り行う葬式のスタイルで、参列者の数の違いが一般葬と大きく違います。言い換えると、葬儀の内容や流れ自体は一般葬と基本的に同じです。
しかし、親しい人物のみが集まる家族葬では、葬儀の内容を比較的自由に決めることができます。つまり、告別式のみ行う家族葬でも、告別式なしで行う家族葬でも問題ありません。
告別式のみ行うということは、通夜がないということです。一日で葬儀が終わることから、一日葬と呼ばれることもあります。
また、告別式がないということは、直接火葬場へ行き火葬するということです。故人が高齢で交友関係が少なくなった場合に、執り行われることが多いです。
なお、直接火葬場に行く葬儀を直葬と呼びます。このように、家族葬における告別式は、親族同士が話し合って内容を決めるのがおすすめです。
家族葬の告別式の流れ
家族葬における告別式の流れは、下記のとおりです。
- 受付
- 開式
- 読経
- 焼香
- 初七日法要
- お別れの儀
- 出棺
基本的な流れは、一般葬と変わりません。参列者が少ないため、全体的にコンパクトです。順番に見ていきましょう。
受付
告別式では、まず参列者を案内するために受付を設置します。受付では、供花や香典を受け取ったり記帳してもらったりしましょう。
また、誰が来ているのか、参列者を把握する意味もあります。ただし、家族葬では、受付を設置しない場合も多いです。
家族葬の参列者は少なく、訪れる方も近しい親族ばかりだからです。また、家族葬では香典を辞退しているケースも多いため、受付を設置する必要性は低いです。
ただ、設置してはいけないわけではないので、どのようにするか状況に合わせて検討しましょう。
開式
あらかじめ決められた時間になると、告別式が開始されます。喪主や遺族は所定の席に着いて、開式を待ちましょう。開式の前に、葬儀社スタッフから説明される場合もあります。僧侶が入場し、告別式が始まります。
読経
告別式が開始されると、僧侶は読経を始めます。読経では故人に戒名が授けられ、現世と別れて仏様のもとに導いてもらうという意味があります。読経は、宗派や僧侶により異なる場合が多いです。
焼香
僧侶が読経をしている間に、喪主や遺族、参列者は焼香をあげます。焼香のやり方も宗派によって異なるため、間違えないように注意しましょう。
基本的に喪主から焼香をあげるため、焼香の仕方がわからない場合は喪主に倣うのがおすすめです。また、葬儀社によっては、開式前の案内で焼香のやり方を説明してくれる場合もあります。
その案内をしっかり確認したうえで、喪主のやり方を確認するのが最も確実です。
初七日法要
家族葬の告別式では、式中に初七日法要を執り行うケースが多いです。初七日法要は、故人が亡くなって7日後に行われる法要ですが、近年では葬儀と同時に行うのが主流です。初七日法要を行うタイミングには、2つのパターンがあります。
- 式中初七日・繰り込み初七日:告別式のあとに続けて行う方法
- 繰り上げ初七日:火葬のあとに行う方法
どちらも告別式と同じく、僧侶の読経中に焼香をあげます。
お別れの儀
焼香が終わり、僧侶が退場したあとは、お別れの儀に進みます。お別れの儀では棺のなかにいる故人と対面し、愛用品やお花を納めます。参列者にとっては、このタイミングが故人との最後の時間となります。
また、お別れの儀では、喪主が挨拶を行います。宗派によってタイミングは若干異なり、僧侶が退場したあとやお別れの儀が終わったあとに行います。
喪主の挨拶では、参列者に対する感謝や生前の故人がお世話になったことへの感謝、これからのお付き合いに関することを述べるのが一般的です。
出棺
お別れの儀が終わったあとは棺に蓋をし、出棺します。その際は、葬儀社スタッフと遺族の男性で棺を運び霊柩車に乗せます。
霊柩車に乗せる際は、棺の向きに注意しなければなりません。一般的に、足から乗せるのが正しいとされています。
ただし、葬儀社のスタッフによって正しい向きになっていることが多いため、特に気にする必要はないでしょう。そのほかにも、葬儀社スタッフの指示に従えば間違いありません。
この後は、火葬や精進落としに進みますが、告別式としてはここで終了となります。
家族葬の告別式にかかる時間
家族葬の告別式にかかる時間は、1時間程度と言われています。ただし、告別式の内容によって異なります。
一般葬と同じ内容でも、参列者が少ないため焼香の時間が短くなりやすいです。一般葬では焼香だけで30分から1時間程度かかる場合もありますが、家族葬では人数によっては5分から10分程度で終わる場合もあります。
そのため、家族葬は一般葬と比べて、短い時間で執り行うことができます。
家族葬の告別式でも基本的に挨拶は必要
家族葬は比較的自由なスタイルで葬儀を執り行えるため、告別式の挨拶を省略してよいものか悩む方もいます。ただし、家族葬であっても、基本的に喪主の挨拶は必要です。
喪主の挨拶には、参列者への感謝の気持ちを示す意味があります。そのため、家族葬であっても、参列者への感謝を示すために挨拶が必要なのです。
ただし、参列者は親しい方ばかりのため、一般葬ほどかしこまる必要はありません。また、挨拶の省略についても正解・不正解はないため、葬儀社や遺族と話し合って決めるのがおすすめです。
なお、下記の記事で家族葬における喪主の挨拶について例文を紹介しています。長男や長女などの立場でも紹介しているので、あわせてご覧ください。
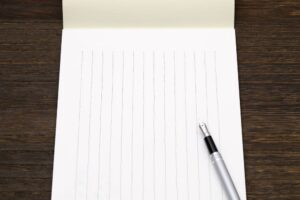
家族葬全体の流れ
家族葬全体は、下記の流れで進行します。
- 逝去から納棺
- 通夜
- 告別式
- 火葬
- 精進落とし
故人が亡くなったと言う連絡を受けてから納棺に至るまでは、慌ただしく時間を過ごさなければなりません。特に、葬儀社を慌てて決めると、思った以上に費用がかかるケースもあります。じっくりと検討したい場合は、事前に見積もりを取っておきましょう。
なお、下記の記事で、家族葬の通夜や火葬の流れを紹介しています。家族葬の全体の流れを知りたい方はご一読ください。

家族葬と一般葬の告別式に大きな違いはない
基本的に、家族葬と一般葬の告別式で大きな違いはありません。参列者の数が少ないだけで、故人への感謝や追悼の気持ちは同じです。
ただし、参列者は近親者のみなので、一般葬ほどかしこまる必要もありません。そのため、ある程度自由な様式で葬儀を執り行うことが可能です。葬儀の形式にとらわれず、遺族でしっかり検討して、納得のいく葬儀を執り行いましょう。
なお、アートメモリーでは、遺族の気持ちを最大限に尊重した葬儀を提供しています。従来の形にとらわれない葬儀をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。








