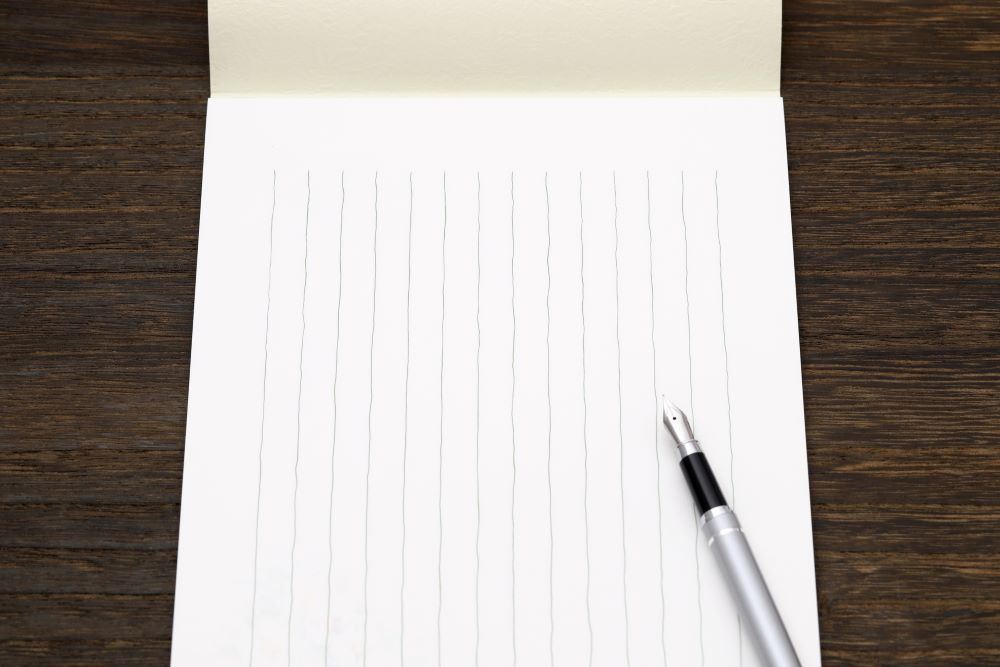家族葬で送る挨拶状を書く機会は少ないため、いざ書くとなるとどう書けばよいのか迷ってしまうものです。家族葬と一般葬で挨拶状の内容に違いがあるのか疑問に思う方もいるでしょう。
正しい書き方や送り方がわからなければ、せっかく心を込めて書いた挨拶状が失礼にあたる可能性もあります。そこで本記事では、下記についてまとめました。
- 家族葬の挨拶状に書くべき内容と例文
- 挨拶状の送り方
- 挨拶状をいつ、誰に送るのか
家族葬の挨拶状に関する内容がわかるので、初めて家族葬を行う方は、ぜひ最後までご覧ください。
家族葬の挨拶状とは
家族葬の挨拶状とは、家族葬が執り行われた後に送る書状です。
家族葬は近親者だけで執り行うものなので、葬儀に参列できなかった方々もたくさんいらっしゃいます。そのような参列できなかった方々に対し、故人が亡くなったことを伝えます。また、事前に案内することなく家族葬として葬儀を終えたことをお詫びしなければなりません。
一般的に、挨拶状は上記を指しますが、ほかにも下記のような書状を指すこともあります。
- 会葬礼状
- 香典返しに添える挨拶状
また、案内状は基本的に縦書きで書きます。ボールペンは使わず、毛筆か万年筆を使いましょう。
喪中ハガキとの違い
挨拶状とよく似たものに喪中ハガキがあります。しかし、挨拶状と喪中ハガキには明確な違いがあるため、しっかりと把握しておきましょう。
喪中ハガキとは「喪中のために新年の挨拶ができない」ことへのお詫びの意味で、一般的に10〜12月に送ります。喪中の期間は慶事を避けるため、年賀状は出しません。喪中ハガキでそのことをお知らせするのです。
このように、家族葬の挨拶状と喪中ハガキは大きく意味が異なりますが、10〜12月に挨拶状を送る場合は喪中ハガキと一体化させる場合もあります。
挨拶状はプリンターで印刷してもよいのか
家族葬の挨拶状を書く際は、以前は手書きが主流でしたが、プリンターを活用した印刷でも問題ありません。重要なのは葬儀がすでに執り行われたということをできる限り早く伝えることです。
手書きは時間がかかるうえに読みづらくなる場合もあるため、現在では印刷したものがよく見られます。なお、挨拶状に対応している葬儀社もあるため、印刷の手間を省く場合は挨拶状の作成を依頼するのもおすすめです。
家族葬の挨拶状に書く内容5つ
家族葬の挨拶状に書く内容は、下記のとおりです。
- 故人が亡くなったことの報告
- 家族葬を執り行ったことのお詫び
- 供花や香典の連絡
- 生前のお礼
- 日付・喪主の住所・氏名
基本的にこの内容を順番に書くだけで、家族葬の挨拶状は完成するため、決して難しいものではありません。具体的な内容を紹介するので、ひとつずつ見ていきましょう。
故人が亡くなったことの報告
挨拶状の最初に、故人との関係性、そして故人が亡くなったことを記載します。病死以外の場合は特に死因の記載はしません。寿命で亡くなった場合は「天寿を全うしました」と書きましょう。また、故人の年齢や亡くなった日にちも添えます。
家族葬を執り行ったことの報告
次に、家族葬を執り行ったことに対する報告とお詫びを記載しましょう。家族葬は一般葬と異なり、喪主から依頼がない限り参列できません。そのため、依頼しなかった方に対してお詫びの気持ちを伝えることが重要です。
また、当然ながら本内容が「家族葬の挨拶状」と「一般葬の挨拶状」における最も大きな違いといえます。本内容を記載する際は、「家族葬は故人の意思」であることを記載すれば、受け取った方にも納得してもらいやすくなります。
供花や香典の連絡
続いて、供花や香典について言及します。参列できなかった方々から香典や供花、供物が送られる場合もあります。手間を減らすことを目的として、家族葬を執り行った場合は、お返しの負担が大きいという理由から供花や香典を辞退するケースも多いです。
そのため、辞退する場合は、相手に気を遣わせないためにも挨拶状で連絡しておくことが重要です。なお、家族葬で辞退するケースが多いというだけで、必ずしも辞退する必要はないので注意しましょう。
また、辞退の旨を連絡したとしても、供花や香典を用意してくれる方がいます。この場合は拒否せず、ありがたくいただきましょう。ただし、お返しを忘れないように注意が必要です。
生前のお礼
挨拶状は、故人が亡くなったことや、家族葬を執り行ったことの報告だけが目的ではありません。故人が生前に受けたご厚誼に対して、お礼を伝えましょう。一文を付け加えるだけで構いません。
日付・喪主の住所・氏名
最後に、日付・喪主の住所・氏名を記載します。日付については西暦ではなく、元号で書くのが一般的です。また、日を省略し、月までにする場合もあります(例:令和五年十月)。基本的に挨拶状は縦書きで書くため、数字は漢数字で記載しましょう。
また、挨拶状に対して緊急の連絡は必要にならないという理由から、電話番号は記載しないのが一般的です。氏名は喪主のフルネームを記載する場合が多いですが、続柄を書いたりほかの家族の名前を書いたりすることもあります。
【パターン別】家族葬で送る挨拶状の例文
挨拶状に書く内容を踏まえて、宗教や挨拶状の種類別に具体的な例文を紹介します。
- 基本的な挨拶文
- 仏教の挨拶文
- 神道の挨拶文
- キリスト教の挨拶文
- 香典返しに使用する挨拶文
- 喪中ハガキと一緒にする場合の挨拶文
基本的な挨拶文を押さえておけば問題ありませんが、ほかの宗教や状況に応じて挨拶文の内容は異なるため、しっかりと押さえておきましょう。順番に紹介します。
基本的な挨拶文
基本的な挨拶状の例文は、下記のとおりです。
| 先日 夫〇〇儀が永眠いたしました葬儀は去る〇月〇日に家族のみで執り行いましたなおご香典 お供物 お花などはご辞退させていただきます生前はひとかたならぬご厚意を賜り深く感謝申し上げますお知らせが遅くなりましたことを深くお詫び申し上げます 〇年〇月〇日住所氏名 |
仏教の挨拶文
仏教で使用する挨拶状の例文は、下記のとおりです。
| 父〇〇儀 天寿を全うし去る〇月〇日永眠いたしました葬儀は故人の遺志により近親者のみにて済ませましたまたこの度〇〇(戒名)四十九日法要と納骨を済ませましたので 合わせてご連絡いたしますなおご香典 お供物 お花などはご遠慮くださいますようお願い申し上げます本来であれば直接お目にかかってお礼申し上げるところではございますが略儀ながら書中にてお礼方々ご挨拶申し上げます 〇年〇月〇日住所氏名 |
神道の挨拶文
神道で使用する挨拶状の例文は、下記のとおりです。
| 父〇〇儀が帰幽いたしました故人の遺志により葬儀は近親者のみで執り行いました生前故人に賜りましたご厚情に深謝申し上げます本来なら直接ご挨拶申し上げるべきではございますが 略儀ながら粗状をもちまして謹んでお礼のご挨拶を申し上げます 〇年〇月〇日住所氏名 |
キリスト教の挨拶文
キリスト教で使用する挨拶状の例文は、下記のとおりです。
| 先般亡祖父 〇〇儀は地上でのつとめを終え天へと召されました故人の生前に皆様より賜りましたご厚情に故人に代わり心より御礼申し上げます葬儀は故人の遺志により近親者のみで執り行いました直接お礼を申し上げるのが本意ではございますが略儀ながら書中にて失礼いたします皆様のもとにも主の慰めが訪れますようお祈り申し上げます 〇年〇月〇日住所氏名 |
香典返しに使用する挨拶文
香典返しに使用する挨拶状の例文は、下記のとおりです。
| 夫〇〇儀 去る(年号)〇年〇月〇日 〇歳にて永眠いたしましたここに謹んでご通知申し上げます葬儀につきましては故人の遺志に基づき 近親者のみにて執り行いました本来ならばすぐにご連絡を申し上げるところではございましたが お知らせが遅れましたことを深くお詫び申し上げますまた 多くのお気遣いとお香典を賜り 深謝申し上げます生前夫に賜りましたご厚誼に深く感謝申し上げます 本来ならば直接ご挨拶し申し上げるところ 恐縮ではございますが略儀ながら書中にてご挨拶とお知らせを申し上げます 〇年〇月〇日住所氏名 |
喪中ハガキと一緒にする場合の挨拶文
喪中ハガキと挨拶状を一緒にする場合の例文は、下記のとおりです。
| 喪中につき新年のご挨拶を失礼させていただきます夫〇〇儀〇月〇日に永眠いたしました早速お知らせするべきところ お知らせが遅れましたことを深くお詫び申し上げます葬儀は故人の希望につき 近親者のみにて執り行いましたお供えやお花 不祝儀につきましては固くご辞退申し上げます故人が生前賜りましたご厚誼につきまして深謝申し上げます 〇年〇月〇日住所氏名 |
挨拶状を送る時期
挨拶状を送る時期については、明確なルールがなく、宗教や宗派によっても異なります。一般的には、香典返しと同様に忌明けが目安です。忌明けとは忌中の終わりのことで、仏教においては四十九日が忌明けとされています。
宗教別に挨拶状を送るべきタイミングは異なるので、下記をご確認ください。
| 宗教 | 挨拶状を送る時期 |
| 仏教 | 忌明けである49日をすぎた頃 |
| 神道 | 忌明けとなる「五十日際」から約1ヵ月後 |
| キリスト教 | プロテスタント:1ヵ月後の記念式カトリック:30日目のミサ |
直葬のように近しい家族しか参列しなかった場合は、忌明けよりも早い時期に挨拶状を送りましょう。親族や親しい友人も参列していなかったため、マナー違反とされません。
また、浄土真宗では「亡くなった方はすぐに極楽浄土に行く」と言う考え方のため忌中がなく、初七日が過ぎたタイミングで挨拶状を送っても問題ありません。
日数が経ってから挨拶状を送った場合、遅れたことで受け取った相手が失礼と感じる可能性があります。挨拶状を送ることは初めから決まっているため、しっかりとスケジューリングして対応しましょう。
家族葬の挨拶状はハガキを使うのが一般的
家族葬の挨拶状は一般的にハガキを使用しますが、ハガキではなくメールや電話で済ませられるケースもあります。たとえば、普段からやりとりしている会社の同僚や友人などです。
ただし、目上の方や年配の方には「失礼」と受け取られる恐れがあるため、その場合はハガキを用意しましょう。このように家族葬の挨拶状に何を使うかは、相手によって使い分けることがおすすめです。
家族葬の挨拶状は誰に送るべきか
家族葬の挨拶状を送るべき相手は、一般葬の場合に参加したと考えられる方々です。故人の交友関係を把握し、近しい家族同士で挨拶状を送るリストを整理しましょう。具体的に挨拶状を送るべき方を挙げると、下記のとおりです。
- 故人・遺族の友人
- 故人・遺族の職場の方々
- 故人と年賀状でやりとりをしていた方
もし、挨拶状を送るべきか悩んでしまう相手がいる場合は、送るのが無難です。挨拶状が送られなかったとトラブルに発展する可能性もあります。したがって、基本的には挨拶状は幅広く送るものと考えておきましょう。
家族葬の挨拶状を書く際の注意点
家族葬の挨拶状を書く際の注意点は、下記のとおりです。
- 句読点は使用しない
- 行頭の一字下げをしない
- 季節の挨拶はしない
- 不適切な言葉を使わない
- 書き損じた場合は、最初から書き直す
不適切な言葉とは、忌み言葉や重ね言葉を指します。たとえば、「死ぬ」「苦しい」は不幸を連想する忌み言葉とされるため、葬儀の場ではふさわしくありません。
さらに、「重ね重ね」「ますます」などは重ね言葉と呼ばれます。重ね言葉は、不幸が連続するという意味で縁起が悪いとされています。日常的に使う言葉が多いので、つい使ってしまわないように注意しましょう。
家族葬の挨拶状を丁寧に書いて感謝を伝える
家族葬の挨拶状は、書く内容が決まっているため、難しいものではありません。ただし、挨拶状を送る時期は、宗教によって異なるため、注意が必要です。送る時期を間違えてしまうとマナー違反とされ、失礼に当たります。
挨拶状は参列できなかった人にお詫びや感謝の気持ちを伝えるものです。誠意を込めて作り、気持ちよく葬儀を締めくくりましょう。
なお、アートメモリーは、お客様のご要望にできる限り応える葬儀社です。家族葬の経験も豊富なので、葬儀社についてお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。