一般葬と比べて規模の小さい家族葬ですが、喪主の必要性は一般葬と変わりません。しかし、家族葬の喪主にどのような役割があるのかわからない方も多いです。
家族葬における喪主の役割をしっかり把握しておかなければ、うまく段取りができず葬儀をスムーズに進められない恐れがあります。
そこで本記事では、下記についてまとめました。
- 家族葬における喪主の役割とやるべき人物
- 喪主がやること7つ
- 家族葬の喪主挨拶
この記事を読むと家族葬の喪主について分かるため、これから家族葬で喪主を務める方におすすめです。
家族葬における喪主の役割
家族葬における喪主は、葬儀の取りまとめ役で、親族の代表です。一般葬との違いはなく、葬儀でやるべきことも変わりません。
また、費用面を管理する施主も兼任する場合は、香典や供花などを管理する必要もあります。親族の代表として、葬儀社スタッフとの打ち合わせはもちろん、僧侶への挨拶や参列者の対応など多くの仕事をこなさなければなりません。
家族葬の喪主は誰がやるべき?
家族葬の喪主は一般葬と同じく、一般的に故人と最も近しい親族が行います。ただし、故人の意向がある場合は、それに従いましょう。
基本的に故人の夫や妻などの配偶者が優先して喪主を務め、その次に長男や長女が喪主を務めます。しかし配偶者が高齢で喪主を務めるのが難しい場合は、形式的に配偶者が喪主を務め、実際の役割は子供が行うこともあります。
家族葬の喪主がやること7つ
家族葬の喪主がやることは、下記のとおりです。
- 各種連絡と手続き
- 葬儀社の決定と打ち合わせ
- その他の事前準備
- お通夜
- 告別式
- 火葬
- 葬儀が終わった後にやること
葬儀が終わるまでの時間は長くありませんが、喪主がやるべきことは数多くあります。葬儀の流れややるべきことをしっかり理解して、喪主の役割を全うしましょう。また、やることリストを作成しておくこともおすすめです。順番に紹介します。
各種連絡と手続き
故人が亡くなった直後にやるべきことは、親戚・知人や菩提寺、葬儀社への連絡と死亡に関する手続きです。まずはご臨終に立ち会ってほしい方に連絡をします。多くの方に連絡するのではなく、「同居している家族のみ」といった少人数に連絡しましょう。
さらに、葬儀社や菩提寺に連絡を取り、葬儀に関する内容を決めます。各種連絡と同時に、死亡に関する手続きも進めましょう。医師から死亡診断書を受け取り、死亡届の必要事項を記入して自治体に提出します。その際、火葬許可証を受け取りますが、実際の届け出は一般的に葬儀社が行います。
葬儀社の決定と打ち合わせ
連絡と手続きが終わればご遺体の安置先を決め、搬送します。ご遺体の安置先は自宅か葬儀社、斎場が一般的です。葬儀を依頼する葬儀社に搬送してもらうことが多いですが、葬儀社をすぐに決められない場合はご遺体の搬送だけを依頼することもできます。
葬儀社を決めたあとは、葬儀の内容について打ち合わせをします。また、故人があらかじめ決めている場合もあるため、遺言をしっかりと確認しましょう。
葬儀者との打ち合わせでは、斎場やプラン、料金などの内容と日程をひとつずつ決めていきます。葬儀の形式を家族葬にする場合は、このタイミングで申し出ましょう。
日程は、菩提寺や火葬場などの都合も確認して決めなければなりません。また、参列者のスケジュールも重要なので「遠方の方が訪れづらい」とならないように、無理のない日程を検討しましょう。
そのほかの事前準備
葬儀の内容や日程が決まれば、残すは細かいところの準備です。具体的には、下記を参考にしてください。
- 遺影に使用する写真を選定
- 葬儀で使用する音楽を選定
- 棺に入れる思い出の品を選定
- 遠方から来る参列所の宿泊先手配
- 葬儀場で受付を依頼したい方への連絡
参列者の多い一般葬では、受付を用意するのが一般的ですが、家族葬では受付を用意しない場合もあります。葬儀当日の香典管理は喪主がやらなければなりませんが、そもそも香典を辞退するケースも多いです。どのような葬儀にするのか、葬儀社や親族としっかり話し合って決めましょう。
なお、家族葬の受付について下記の記事で詳しく解説しているので、受付についてお悩みの場合はあわせてご覧ください。

お通夜
お通夜でやるべきことは、あまり多くありません。まずは、開始時間の1〜2時間前に斎場へ行き、納棺や供花の準備をしましょう。
お通夜が始まると、基本的にお通夜の進行には関わりません。お通夜の開始前に来訪する参列者の対応をします。お悔やみの言葉をかけられたら、丁寧にお礼を述べましょう。また、僧侶が到着した際は、出迎えして挨拶をします。
お通夜では焼香が終わり、僧侶が退出したタイミングで、喪主として挨拶を述べます。喪主の挨拶は参列者への感謝を示すものなので、基本的に省略しません。ただし、参列者が家族だけといった場合は、省略するケースもあります。
お通夜が終わったあとに通夜振る舞いを用意している場合は、その会場へ誘導します。通夜振る舞いでも、開始時と終了時に挨拶が必要です。お通夜が終了したあと、葬儀社スタッフと翌日の打ち合わせをします。
ただし、一日葬の場合は、お通夜そのものが省略されます。
告別式
告別式で喪主がやるべきことは、お通夜同様に、一般葬と大きく変わりません。
まずは、開式前に弔辞や弔電の確認をし、読み上げてもらうものを選びます。火葬場へ移動する車の手配も必要なため、斎場から火葬場へ移動する人数や精進落としの人数も確認し、葬儀社スタッフに伝えましょう。
参列者が訪れはじめたら丁寧に対応しましょう。また、僧侶が到着したら挨拶にうかがいます。葬儀が始まると特にやることはありませんが、参列者の焼香の際に座ったままで、参列者に黙礼します。
出棺の際は、喪主がご位牌、ほかの遺族は遺影を持つのが一般的です。出棺時に挨拶をしますが、お通夜同様に参列が家族のみの場合などは挨拶を省略する場合もあります。
火葬
火葬場では、故人と最後のお別れをし、火葬後に収骨します。収骨は、喪主から始めるのが一般的です。足の骨から順番に収めていき、最後の喉仏は喪主が収めます。
収骨が終われば葬儀場に戻り、初七日法要を行ったあと、精進落としが振る舞われます。精進落としでは、開始時と終了時に簡単な挨拶をしましょう。なお、初七日法要のタイミングは、地域や葬儀社などによって異なります。
葬儀が終わったあとにやること
喪主は、葬儀中よりも葬儀が終わったあとにやることが多いといわれています。具体的には、下記のとおりです。
- 香典の確認
- 香典返しの手配
- 補助金や保険などの手続き
- 参列できなかった方へ挨拶状の手配
家族葬を行う場合、一般葬なら呼ぶ方々に対して挨拶状で連絡しなければなりません。挨拶状では、すでに親戚のみで葬儀を執り行ったことに対するお詫びを述べます。
下記の記事で、挨拶状について例文付きで解説しているので、書き方を詳しく知りたい方はご一読ください。
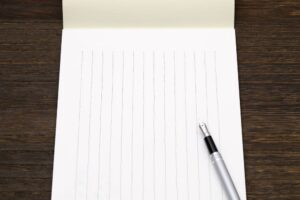
【例文あり】家族葬の喪主挨拶
家族葬では「喪主の挨拶はなしでも良い」と考える方もいますが、一般葬と変わらず喪主は挨拶するのが一般的です。喪主の挨拶は、参列者への感謝や生前の故人へのご厚誼に対する感謝、今後も変わらずお付き合いくださることへのお願いが込められています。
また、喪主の挨拶といえばお通夜や告別式で参列者に対する挨拶を指す場合が多いですが、ほかにも挨拶をするタイミングは多いです。たとえば、僧侶への挨拶や通夜振る舞い、精進落としなどが挙げられます。
僧侶への挨拶を除き、参列者が家族のみの場合に堅苦しくする必要はありません。下記は、告別式で使用できる挨拶の例文です。カンペを使っても問題ないため、ぜひ参考にしてください。
| 本日はご多用の中ご参列賜りまして誠にありがとうございます。 故人も、こうしてみなさまにお集まりいただき、さぞかし喜んでいることと存じます。 今後は生前の故人に接したと同様、残された遺族にもご厚情を賜りますよう、ひとえにお願い申し上げる次第でございます。 簡単ではございますが、お礼の挨拶にかえさせていただきます。ありがとうございました。 |
なお、下記の記事で家族葬における喪主の挨拶について、例文付きで紹介しています。息子や娘など立場ごとに紹介しているので、すぐに使える例文を知りたい方はご覧ください。

家族葬の喪主が着用する服装
家族葬における喪主の服装は、一般葬と変わらず正喪服や準喪服が基本です。正喪服の場合は和装もありますが、洋装で問題ありません。
男性の場合はネクタイや靴などを黒で統一し、結婚指輪以外のアクセサリーはつけず、ネクタイピンも外します。また、ベルトや靴は光沢がないものを選びましょう。
女性の場合も、バッグやストッキングなどの小物は黒に統一します。ブラックを基調としていれば、パンツスタイルでも大丈夫です。結婚指輪以外のアクセサリーは避けなければなりませんが、真珠のネックレスやイヤリングは問題ありません。
やることを整理して喪主の役割を全うしよう
喪主の役割は、家族葬と一般葬で違いはなく、参列者への対応や挨拶が基本です。一方で、葬儀前や葬儀後にこそ、やるべきことが多いことも忘れてはいけません。
喪主をする機会は少ないため、何をすべきか分からない方も多いと思います。その場合は、葬儀社スタッフや喪主の経験がある親族としっかり話し合い、思い出に残る葬儀を実現しましょう。
なお、葬儀社選びにお悩みの場合は、アートメモリーがおすすめです。アートメモリーはお客様の要望にできる限り応える葬儀社です。喪主の方が疑問に思うことや困っていることを解決します。これから家族葬で喪主を務める予定の方は、お気軽にお問い合わせください。








